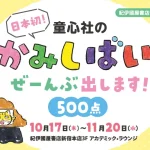穴八幡宮の由緒と歴史
金運・開運のパワースポットとして知られる穴八幡宮は、平安時代の武将・源義家が前九年の役(1051~1062年)の戦勝を感謝し創建したと伝わる古社です。創建からおよそ千年、新宿の地で人々の信仰を集め続けてきました。

正面参道に立つ朱色の大鳥居は、早稲田通りと諏訪通りが交差する馬場下町交差点に位置します。足元をよく見ると、なんと石造りの亀が鳥居を支えているのが分かります。ぜひ訪れた際は、細部まで観察してみてくださいね。
参道を進むと現れるのは、鮮やかな朱色が印象的な荘厳な隋神門(ずいじんもん、別名:光寮門)。江戸時代の嘉永2年(1849年)に竣工しましたが、昭和20年の空襲で焼失。しかし、人々の強い思いが実を結び、平成10年(1998年)に見事に再建されました。その美しい姿には、復興への祈りが込められています。
実は、「穴八幡宮」という珍しい名前には、特別な由来があります。寛永18年(1641年)に社殿を造営していた際、地下から横穴が出現し、その中から金銅の阿弥陀如来像が発見されたのです。この神秘的な出来事から、その名が付いたとされています。現在の社殿は、まさにこの横穴が発見された場所に建っているんですよ。
穴八幡宮と放生寺の関係

穴八幡宮の隣には、同じく長い歴史を持つ放生寺(ほうしょうじ)があります。かつては神仏習合により一体とされ、江戸時代までは神と仏を共に祀る神聖な空間でした。現在もその名残から、両方の寺社をあわせて参拝することで、金運と健康運など異なるご利益を一度に願えると伝えられています。
参拝の際は、まず穴八幡宮を参拝し、次に放生寺を訪れるのが一般的です。開運パワーを授かるため、ぜひ両社を巡ってみてください!

正面参道鳥居の先にある北参道には、もう一つの石造りの鳥居が佇みます。鳥居の脇には小さな公園があり、参拝の合間にひと息つくのに最適です。
また、早稲田通り沿いに立つ青銅製の鳥居は、なんと日本で2番目の大きさを誇る貴重な存在です。青銅鋳物製の一体型鳥居として知られ、貫には菊の御紋と3羽の鳩が精巧に施されています。その迫力と美しさをぜひ見上げて、間近で体感してください。
ご利益で人気!一陽来復御守の貼り方とは?
穴八幡宮の名物「一陽来復御守(いちようらいふくおまもり)」は、特に金運アップを願う人々に絶大な人気を誇るお守りです。冬至から節分までの限られた期間しか手に入らないため、毎年多くの参拝客が列をなします。テレビや雑誌でも多数紹介され、有名人や起業家の方々もお詣りに訪れているとか。
一陽来復とは「悪い流れが終わり、良い方向に転じる」ことを意味する、強力な開運守りです。ご利益を最大限に得るために最も重要なのは、「冬至・大晦日・節分のいずれかの夜中0時」に「その年の恵方」を向いて貼ること。リビングやオフィス入口など、できるだけ高い位置に貼るのが効果的とされています。恵方は毎年変わるので、事前に確認しましょう。
御守は、和紙のりなどで台紙を使わず、壁や柱に直接貼ってください。画鋲で刺したり、上からテープで全面を覆い押さえつけるのは避けるよう伝えられています。もし神棚や他の御守と並べる場合は、上下の差をつけず、横に並べて貼るようにしてください。
授与場所は境内の授与所です。貼るタイプ(初穂料1,000円)と、懐中御守(400円)の2種類があります。例年、早朝から夕方まで頒布されますが、時期によって時間が変更される可能性があるので、必ず事前に公式SNS(Xや公式サイトなど)で最新情報を確認してからお出かけください。
- ご利益:金運や開運
- 授与期間:冬至から節分の間
- 授与場所:境内の授与所
- 種類/金額:一陽来復御守(貼るタイプ)1,000円、一陽来復懐中御守(財布に入れるタイプ)400円
- お祀りする日時:冬至・大晦日・節分の夜中0時(恵方を向いて)
穴八幡宮の流鏑馬と年中行事

穴八幡宮では、毎年9月15日に例大祭が開催され、その中でも流鏑馬(やぶさめ)は必見!馬上から矢を放つ、弓を構え疾走する武者の勇壮な姿は歴史絵巻のよう。武士の技を現代に伝えるこの神事は、江戸時代から続く伝統行事で、毎年観客からは大きな歓声が上がります。
また、毎月1日と15日には月次祭が行われ、神楽の奉納が地域の人々の心を静かに癒します。
現在、近隣の高田馬場で行われる高田馬場流鏑馬も、元々は穴八幡宮に深く根ざした神事であり、毎年10月の第2月曜日に開催されています。
流鏑馬の臨場感あふれる取材レポートはこちらの記事でご覧いただけます!
◆【高田馬場流鏑馬】勇壮な伝統文化!迫力満点の馬上弓術を取材レポート
初めて参拝する方には、基本的な神社の作法を事前にチェックしておくことをおすすめします。
◆神社参拝の作法を学ぼう!
新宿区にある他の神社の歴史や特徴については、こちらの記事をご参照ください。
◆新宿区にある神社13選|歴史と文化を感じよう!
基本情報
| 神社名 | 穴八幡宮 |
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2-1-11 |
| TEL | 03-3203-7212 |
| アクセス | 東京メトロ東西線「早稲田駅」下車、3B出口より徒歩5分 |
| 開門、閉門時間 | 拝殿:6:00~17:00、幣殿:9:00~16:00、社務所:9:00~17:00、公衆トイレ:9:00~16:30(それ以外の時間は有料) |
※時間、お休みなどの情報は変更されている場合があるので、最新情報は直接確認してください。
周辺MAP
(文:鶴田智美)